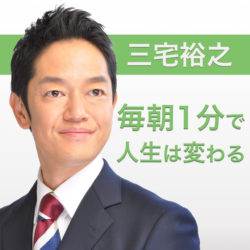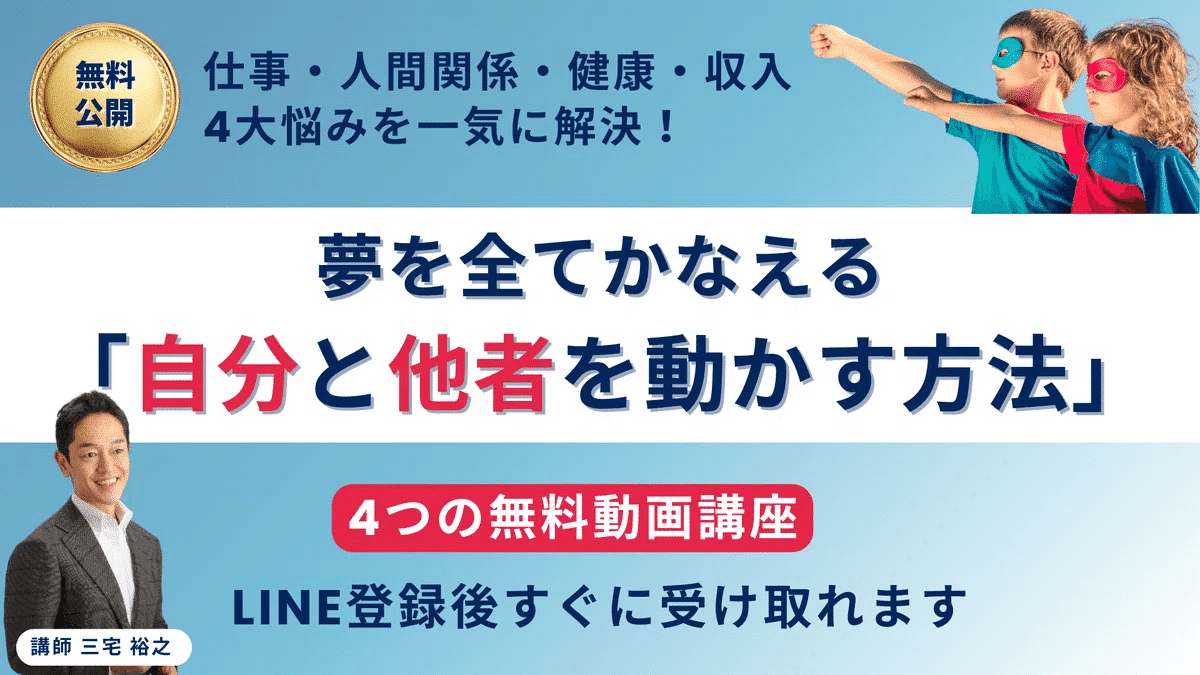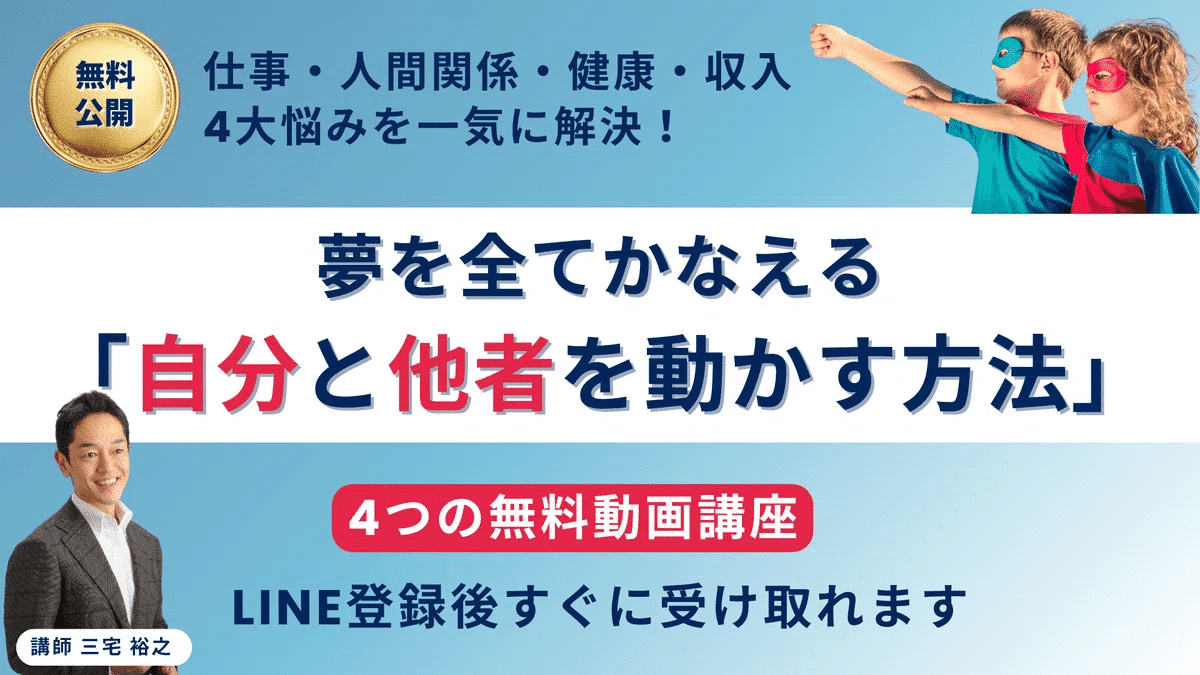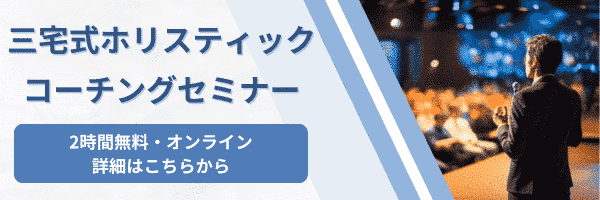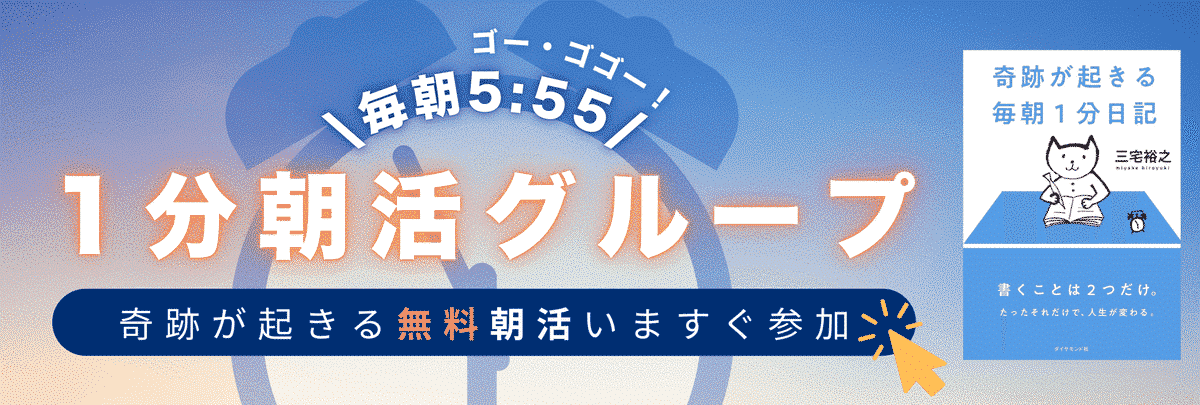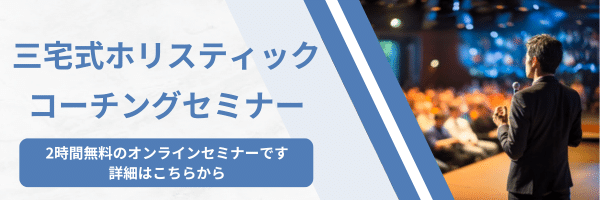結果を出す起業家はぶっちゃけ図々しい人が多い。
いきなり「今月会いたい」「人を紹介してほしい」と言ってくる。
ただ、それを失礼だと感じさせない愛嬌や人間力がある。
自分の魅力をわかった上でのワガママさ。
人の懐にスッと入り、いつのまにか信頼を獲得している。
「これを言ったら相手がどう思うかな?」
などは百も承知でガンガン攻めてくるのが起業家です。
何も起業家に限らず、人生ではどんどんリクエストした方がいい。
リクエストはスキル。
ポイントは「断られて元々。受け入れてくれたらラッキー」と思うこと。
失うものは大してないんですよ。
みんな図々しくなっていい。
失礼と感じさせない愛嬌や人間力って言うのは、「素直さ」や「感謝」や「貢献の意識」
アドバイスしたことは素直にやってみるし、具体的なお礼など感謝を大切にするし、とにかく何か相手に貢献できないか恩返しできないかをちゃんと考えている。
まあ、多少図々しくて生意気な人でいいんですよ。
何度も鼻をへし折られることよって、人間性もできてくるから。
現在、LINEで無料動画講座を開催中です。
あなたのキャリア、人間関係、健康、経済、すべてを大きく飛躍させるための全4回の講座です。
お届けするコンテンツはすべて無料でご覧いただけます。
10秒ほどで簡単に登録できますので、以下からどうぞ。
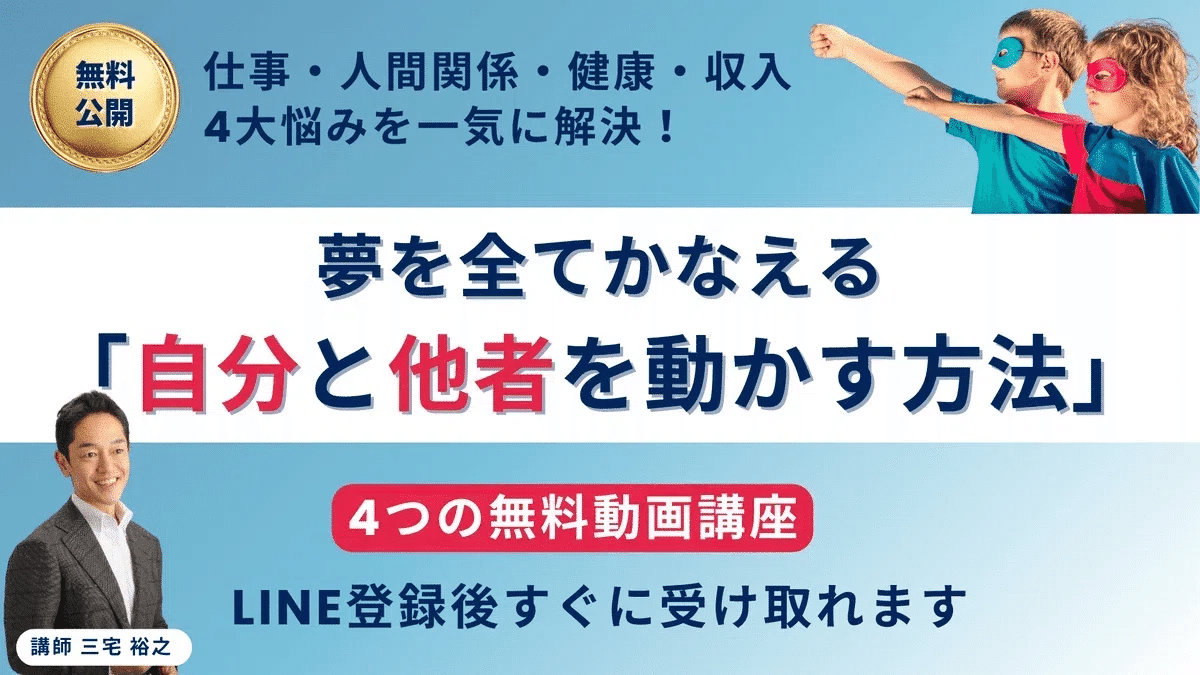
動画を視聴してくださった方には、豪華3大特典もプレゼントいたします。
①現状突破ワークブック
②最強コンディション管理手帳
③才能×スキル=収益化ハンドブック
ぜひお受け取り下さいませ。
今回のお話は音声でも聴くことができます。以下から再生してください↓
Podcast: Play in new window | Download