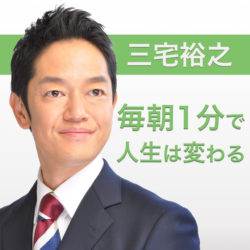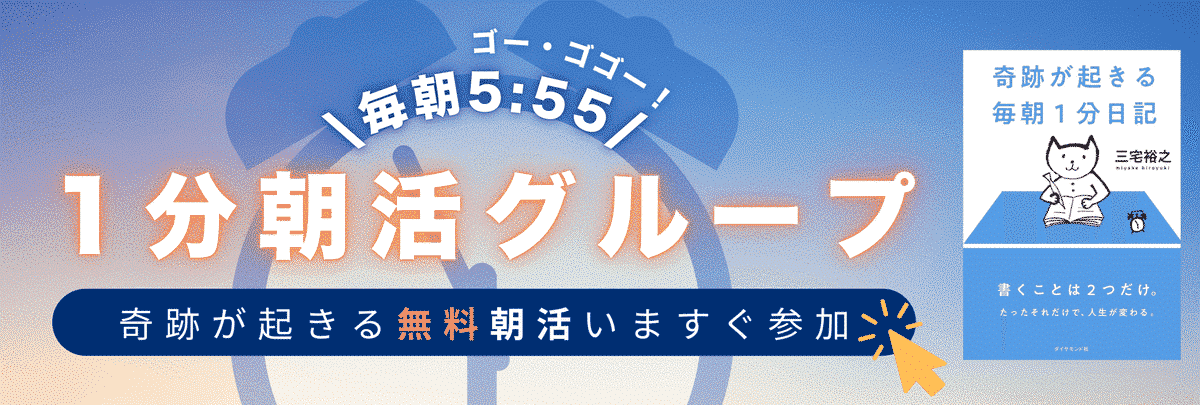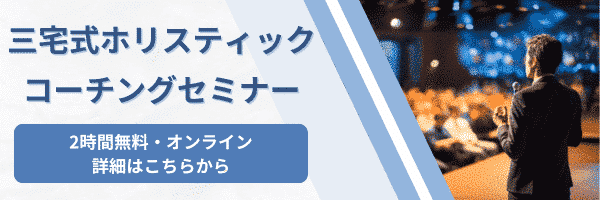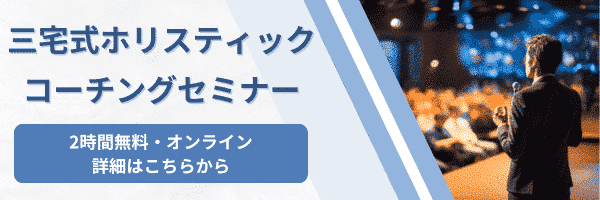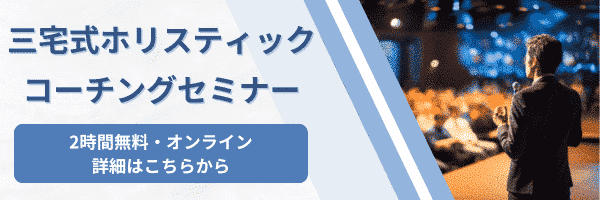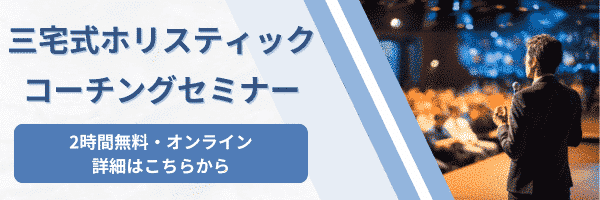部下に手を出すほど、成長の芽はしぼむ
ハーバード大学で最も人気を集めるリーダーシップの講義を担当するロナルド・ハイフェッツ教授は、優れたリーダーの条件として「ワークバック」を挙げています。
ワークバックとは、部下が抱える課題をすぐに奪わず、相手に返す姿勢のこと。
シンプルだけれど、かなり本質的な考え方です。
多くのリーダーは、困っている部下を見ると反射的に手を差し伸べてしまいます。
指示を出し、方向を示し、時には解決まで代わりにやってしまう。
短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的にはチーム全体の思考力を削り取ることになる。
リーダーが必ず答えを持っている前提が続くと、人は考えることをやめてしまうからです。
答えるリーダーから、考えさせるリーダーへ
ハイフェッツ教授は明言します。
リーダーの役割は「答えること」ではなく、考えさせ、実行させ、結果を出させることだと。
リーダーが全部を抱え込む組織は、表面上は順調に見えても、内側では育成の機会が失われています。
部下の悩みや迷いこそ、成長の種。そこに踏みとどまり、試行錯誤する時間を奪われてしまえば、人は強くなれない。
成長の痛みを引き取ってしまうリーダーほど、優しいようで組織の未来を閉ざしてしまう皮肉もある。
ダンスフロアとバルコニー
ハイフェッツ教授がよく使う比喩があります。
それが「ダンスフロア」と「バルコニー」という二つの視点。
ダンスフロアは、現場の渦中に入り込み、今まさに起きている課題に向き合う場所。
一方でバルコニーは、一段上から全体を俯瞰し、流れや構造を読み取る場所。
優れたリーダーは、この二つを行き来しながら状況を調整していきます。
どちらか一方に偏ると、組織は動きを失う。
現場だけ見ていると視野が狭くなり、俯瞰だけしていると現実感を失う。
だからこそ行き来が必要になる。
絶妙なバランスが、組織の生命線です。
課題を返す勇気
部下が悩み、考え込み、何度もやり直す時間こそが、成長の源泉です。
そこでリーダーが「代わりにやってあげるよ」と言ってしまうと、その瞬間は安心を与えられますが、長期的には依存を生む。
組織はリーダーがいないと動けない状態に固まっていきます。
だからこそ、課題を返す勇気が必要になります。
一見すると冷たい態度に見えるかもしれません。
しかし本気で育てたいなら、あえて一歩引く姿勢が不可欠。
「やってみましょう」
「どうすればできそうですか」
そんな問いを返すことで、部下の中に思考が芽生える。
責任と主体性が生まれてくる。
ワークバックとは、突き放すことではなく、信頼の表現です。
伸びる人は、自分で掴んだ答えを持って進む。
リーダーは、その力を引き出す存在。
育てる覚悟
人を育てるとは、時間がかかる行為です。
効率だけを求めると、どうしてもリーダーが先回りしがちになる。
けれど、短期の効率と長期の成長は一致しない。
未来をつくるリーダーほど、不器用に見える選択をあえて取っていきます。
ワークバックとは、覚悟の姿そのもの。
部下を信頼し、主体性を託し、成長の痛みすら尊重するリーダーの在り方です。
チームが強くなる道筋は、ここにあります。
現在、LINEで無料動画講座を開催中です。
あなたのキャリア、人間関係、健康、経済、すべてを大きく飛躍させるための全4回の講座です。
お届けするコンテンツはすべて無料でご覧いただけます。
10秒ほどで簡単に登録できますので、以下からどうぞ。
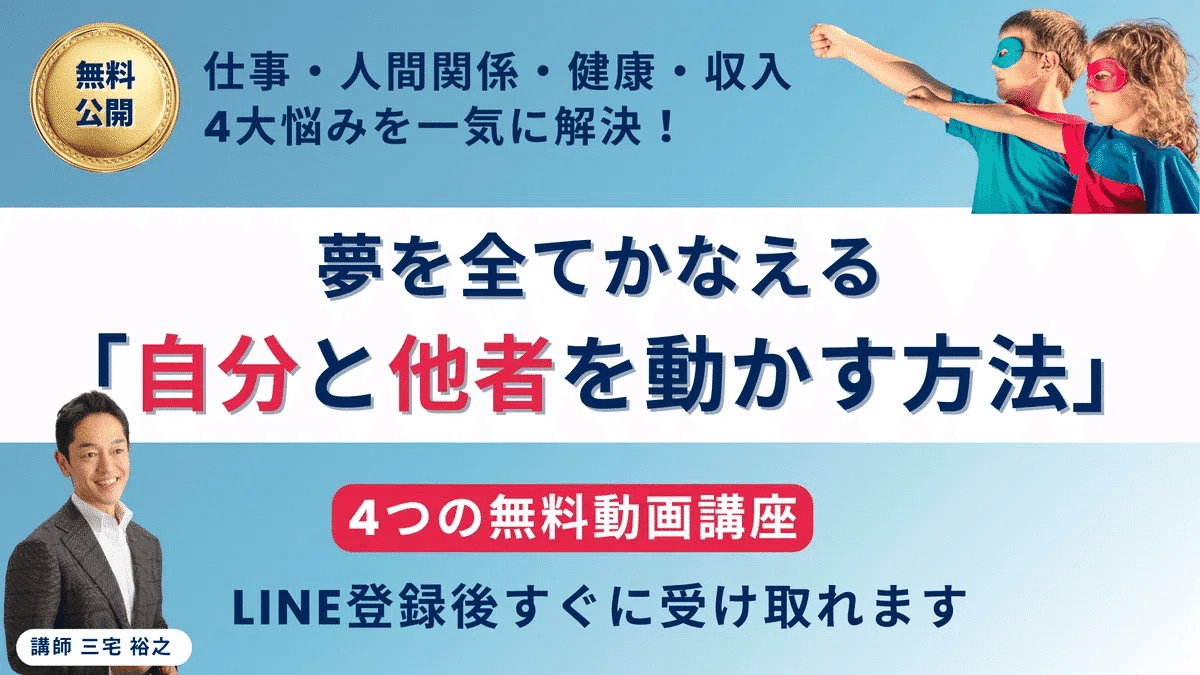
動画を視聴してくださった方には、豪華3大特典もプレゼントいたします。
①現状突破ワークブック
②最強コンディション管理手帳
③才能×スキル=収益化ハンドブック
ぜひお受け取り下さいませ。
YouTube、X、Facebook、Instagram、Voicy、note、amebloなど、
各種SNSへはこちらから↓
https://lit.link/hm1
今回のお話は音声でも聴くことができます。以下から再生してください↓
Podcast: Play in new window | Download