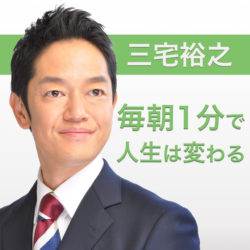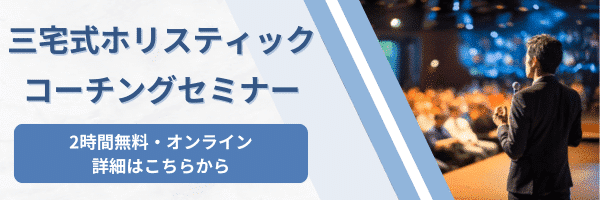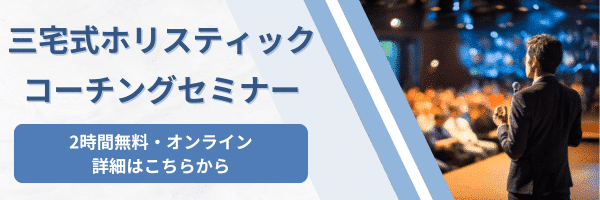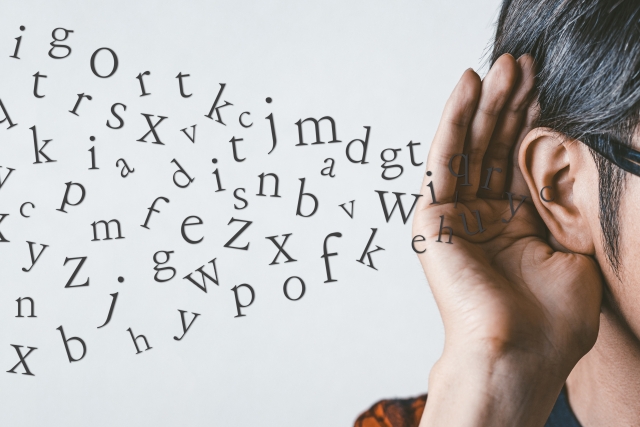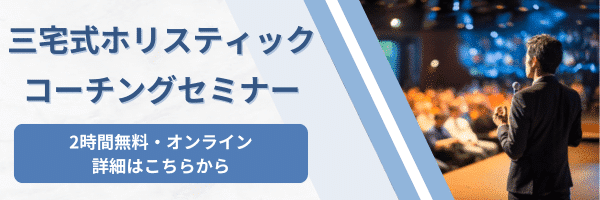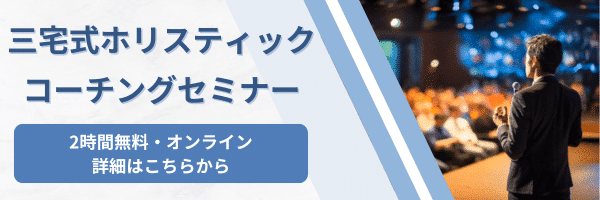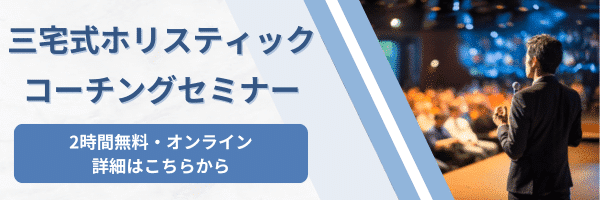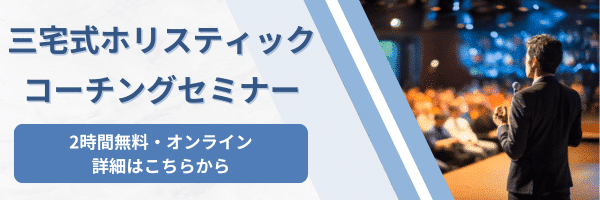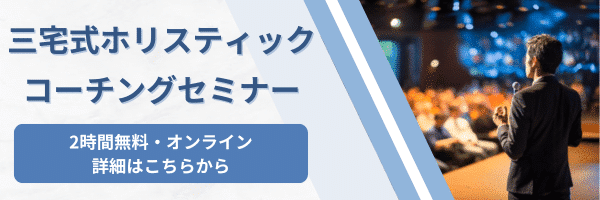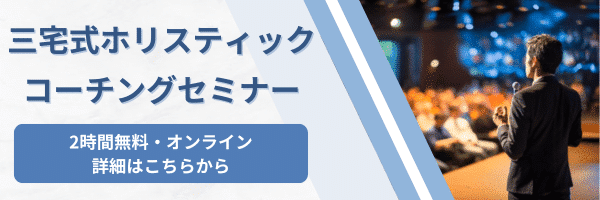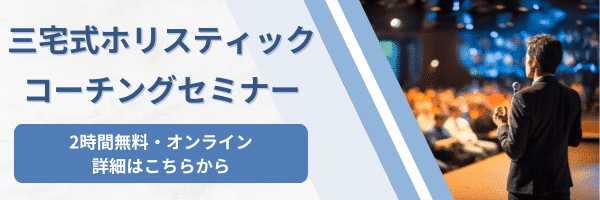インド人の友人が
「日本人は会議の遅刻は許さないけど終了時間は平気で延長する」
「日本人は家族がいるのに残業を平気でやる」
と驚いていた。
日本の”普通”は海外から見たら”異常”なので、当たり前に慣れ過ぎると一瞬で信用を失う。
「郷に入れば郷に従え」では外国人のマネジメントは無理です。
また、日本人と中国人・インド人は「時間の流れ方」も違います。
日本やドイツは「単一時間(モノクロニック)」と言って、順番を大切にする文化。
予定変更を嫌う。
一方、中国やインドは「多元的時間(ポリクロニック)」と言って、順番より機会を大切にするので予定変更は当たり前。
このあたりも良い悪いではなく、違いがあることを知っておくことが大切。
今日も素敵な1日を。
ただいま、無料コーチングセミナー開催中です。
「家族や時間を犠牲にせず、成果を出したい」
そんな方に向けて、今日からすぐに使える技術をお伝えしています。
ぜひご参加くださいませ。詳しくは以下からどうぞ。
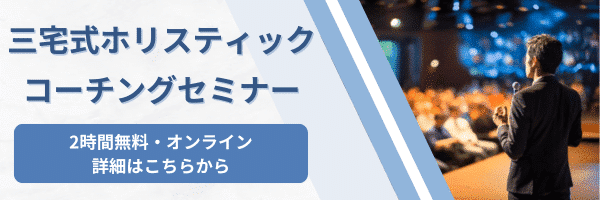
YouTube、X、Facebook、Instagram、Voicy、note、amebloなど、
各種SNSへはこちらから↓
https://lit.link/hm1
Podcast: Play in new window | Download